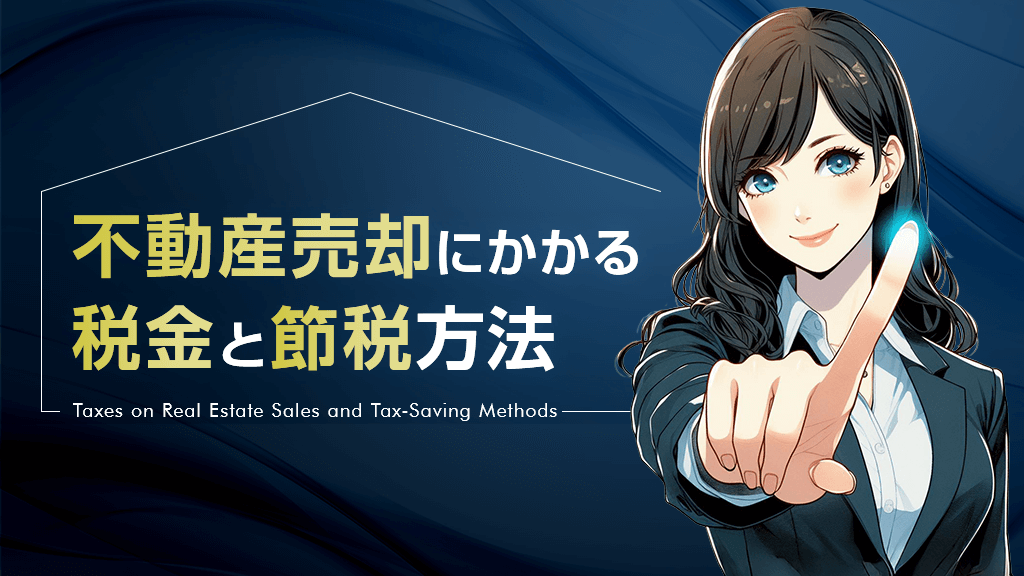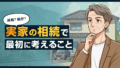不動産売却時にかかる税金の計算方法や節税対策を知らないと、損をしてしまう可能性があります。
この記事では、不動産売却で発生する税金の種類から、具体的な計算方法、節税の特例まで解説します。
さらに、確定申告の流れやよくある疑問にもお答えし、税金に関する不安を解消し、安心して不動産売却を進められるようサポートします。
▼ お気軽にお見積もりをご依頼ください!
関西エリアの空き家物件のご売却はお任せください!築古・郊外・訳あり物件も歓迎です!部屋に荷物が残っていても、現状買取が可能です。まずはお気軽にご相談ください!
不動産売却で発生する税金の種類と全体像
不動産の売却に関連する税金はいくつかの種類があります。
その仕組みを理解していないと、思わぬ納税額に驚いたり、適用できるはずの特例を見逃して損をしたりする可能性があります。
この章では、不動産売却で発生する主要な税金の種類と、それぞれの税金がどのような状況で発生するのかを全体像として解説します。まずは、売却益にかかる最も重要な税金である「譲渡所得税」から見ていきましょう。
不動産売却で最も重要な譲渡所得税とは
不動産売却で発生する税金の中で、最も大きな割合を占めるのが「譲渡所得税」です。これは、不動産を売却して得た利益、つまり「譲渡所得」に対して課される税金を指します。不動産の購入時よりも売却時の価格が高かった場合に発生し、その利益に対して税金がかかる仕組みです。
利益が出なければ原則として課税されませんが、特例を適用するために確定申告が必要なケースもあります。
譲渡所得税の内訳 所得税・住民税・復興特別所得税
譲渡所得税は、国に納める「所得税」、居住地の地方自治体に納める「住民税」、そして東日本大震災の復興財源に充てられる「復興特別所得税」の3つの税金で構成されています。それぞれの税金は、譲渡所得に対して一定の税率を乗じて計算されます。
- 所得税:国税であり、譲渡所得に対して課税されます。
- 住民税:地方税であり、譲渡所得に対して課税されます。市区町村と都道府県にそれぞれ納めます。
- 復興特別所得税:東日本大震災からの復興財源を確保するため、2013年(平成25年)から2037年(令和19年)までの期間、所得税額に対して2.1%の税率で課される税金です。譲渡所得税の場合も、所得税額にこの税率が加算されます。
これらの税率は、不動産の所有期間によって異なり、長期所有か短期所有かで大きく変動します。詳細な税率については、次章「不動産売却にかかる税金 譲渡所得税の計算方法を徹底解説」で詳しく解説します。
不動産売却時にかかるその他の税金
譲渡所得税以外にも、不動産売却時にはいくつかの税金が発生する可能性があります。これらは売却の状況や契約内容によって発生の有無が異なります。
印紙税
印紙税は、経済的な取引を伴う契約書や領収書などに課される国税です。不動産売却においては、「不動産売買契約書」の作成時に必要となります。契約書に記載された契約金額に応じて税額が定められており、契約書に収入印紙を貼り付け、消印することで納税します。
印紙税の税額は以下のとおりです。税額は法改正により変更される場合がありますので、最新の情報は国税庁のウェブサイトでご確認ください。国税庁
| 記載された契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上50万円以下 | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 400円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 60,000円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 100,000円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 200,000円 |
| 50億円を超えるもの | 400,000円 |
不動産売却にかかる税金 譲渡所得税の計算方法を徹底解説
不動産売却で発生する税金の中で、最も大きな割合を占めるのが譲渡所得税です。この税金は、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課税されるものです。
譲渡所得税の計算式を理解する
譲渡所得税は、不動産の売却によって得た「譲渡所得」に対して課税されます。譲渡所得は、以下の計算式で求められます。
この計算式で算出された譲渡所得に、所有期間に応じた税率を掛けることで、最終的な譲渡所得税額が決定されます。
それぞれの項目が何を指すのか、詳しく見ていきましょう。
譲渡価格とは
不動産売却における譲渡価格とは、売却代金そのものを指します。具体的には、買主から受け取る売買契約書に記載された金額です。
ただし、売却年の固定資産税を買主が負担する期間がある場合、その期間分の税金相当額を売却代金に上乗せして受け取ることがありますが、これも譲渡価格の一部として扱われます。
取得費とは
取得費とは、売却した不動産を取得するためにかかった費用の総額です。譲渡所得を計算する上で、譲渡価格から差し引くことができる重要な項目です。
取得費には、たとえば以下のような費用が含まれます。
- 不動産の購入代金:土地や建物の購入費用そのもの。
- 購入時の諸費用:
- 仲介手数料(不動産会社に支払った手数料)
- 印紙税(売買契約書に貼付した印紙代)
- 登録免許税(所有権移転登記などにかかる税金)
- 不動産取得税(不動産を取得した際にかかる税金)
- 司法書士への報酬(登記手続きの依頼費用) など
取得費が不明の場合は、譲渡価格の5%として計算されるため、取得費がわかっている場合に比べて税金が高くなります。
内容が難しい話ですが、要は領収書などの証拠書類の保管場所をしっかり把握しておくことが重要ということです。
譲渡費用とは
譲渡費用とは、不動産を売却するために直接かかった費用のことです。これも収入金額から差し引くことができる項目です。
譲渡費用に含まれる主な項目は以下のとおりです。
- 仲介手数料:不動産会社に支払った売却時の手数料。
- 印紙税:売買契約書に貼付した印紙代。
- 測量費:土地を売却する際に境界を確定するために行った測量費用。
- 建物の取り壊し費用:建物を解体して更地で売却した場合の解体費用。
- 売買契約書作成費用:司法書士や行政書士に依頼して作成してもらった費用。
修繕費や固定資産税、ローンの繰上返済手数料などは、譲渡費用には含まれませんので注意が必要です。
所有期間による税率の違い
不動産売却による譲渡所得にかかる税率は、売却した不動産の所有期間によって大きく異なります。所有期間は、売却した年の1月1日時点で判断されます。
具体的には、不動産の所有期間が5年以下か5年超かによって、適用される税率が「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分かれます。
短期譲渡所得の税率
売却した年の1月1日時点で、不動産の所有期間が5年以下の場合は、「短期譲渡所得」とみなされ、高い税率が適用されます。
| 税金の種類 | 税率 |
|---|---|
| 所得税 | 30.63% (復興特別所得税を含む) |
| 住民税 | 9% |
| 合計税率 | 39.63% |
長期譲渡所得の税率
売却した年の1月1日時点で、不動産の所有期間が5年を超える場合は、「長期譲渡所得」とみなされ、短期譲渡所得よりも低い税率が適用されます。
| 税金の種類 | 税率 |
|---|---|
| 所得税 | 15.315% (復興特別所得税を含む) |
| 住民税 | 5% |
| 合計税率 | 20.315% |
このように、所有期間が5年を超えるかどうかで税率が大きく変わるため、売却のタイミングを検討する際には、この所有期間の基準を意識することが非常に重要です。
より詳細な情報は、国税庁のウェブサイトで確認することができます。
不動産売却の税金を抑える!知らないと損する節税対策と特例
不動産売却で発生する税金は高額になりがちですが、さまざまな特例や控除を適用することで、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
ご自身の状況に合った特例がないか確認しましょう。
居住用財産を売却した場合の3,000万円特別控除
ご自身が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例です。この特例を適用できれば、譲渡所得が3,000万円以下であれば税金がかからないことになります。
主な適用要件は以下のとおりです。
- 売主が住んでいる家屋とその敷地を売却すること。
- 住まなくなった日から3年を経過した年の12月31日までに売却すること。
- 売却した年の前々年、前年にこの特例の適用を受けていないこと。
- 売却した家屋や敷地について、買換え特例など他の特例の適用を受けていないこと。
- 親子や夫婦など、特別な関係にある人に対して売却したものでないこと。
この特例は、居住用財産を売却する際の最も強力な節税策の一つであり、多くのケースで利用が検討されます。
詳細な要件や適用条件については、国税庁のウェブサイトをご確認ください。No.3302 マイホームを売ったときの特例(国税庁)
居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例
マイホームを売却し、その所有期間が、売却した年の1月1日時点で10年を超えている場合、譲渡所得に対して軽減税率が適用される特例です。
主な適用要件は以下のとおりです。
- 売主が住んでいた家屋とその敷地を売却すること。
- 売却した年の1月1日において、その家屋と敷地の所有期間が10年を超えていること。
- 売却した年の前々年、前年にこの特例の適用を受けていないこと。
- 親子や夫婦など、特別な関係にある人に対して売却したものでないこと。
この特例が適用されると、譲渡所得の金額のうち6,000万円以下の部分について、以下の軽減税率が適用されます。
| 税金の種類 | 税率 |
|---|---|
| 所得税 | 10% |
| 住民税 | 4% |
| 復興特別所得税 | 所得税額の2.1% |
| 合計 | 14.21% |
通常の長期譲渡所得の税率(20.315%)と比較して、約6%低い税率で計算されるため、税負担を大きく軽減できます。
また、この特例は、上記の3,000万円特別控除と併用することができます。
詳細な要件や適用条件については、国税庁のウェブサイトをご確認ください。No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例(国税庁)
特定の居住用財産の買換え特例
特定の居住用財産(マイホーム)を売却し、代わりに新たな居住用財産を購入した場合に、譲渡所得の課税を将来に繰り延べることができる特例です。これは税金が免除されるわけではなく、課税が繰り延べられるという点に注意が必要です。
主な適用要件は以下のとおりです。
- 売主が住んでいた家屋とその敷地を売却すること。
- 売却した年の1月1日において、その家屋と敷地の所有期間が10年を超えていること。
- 売却価格が1億円以下であること。
- 売却した年の前年、当年、翌年の3年以のうちに新たなマイホームを取得し、住み始めること。
- 新たなマイホームの床面積が50㎡以上であること。
- 新たなマイホームの取得価額が、売却したマイホームの譲渡価額以上であること。
- 親子や夫婦など、特別な関係にある人に対して売却したものでないこと。
この特例は、3,000万円特別控除や軽減税率の特例とは選択適用となり、併用はできません。どちらの特例がご自身の状況に有利かを慎重に検討する必要があります。
詳細な要件や適用条件については、国税庁のウェブサイトをご確認ください。No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例(国税庁)
相続した空き家を売却した場合の3,000万円特別控除
相続によって取得した空き家とその敷地を売却した場合に、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例です。この特例は、空き家問題の解消を目的として設けられました。
主な適用要件は以下のとおりです。
- 相続開始直前まで被相続人(亡くなった人)が居住していた家屋であること。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震基準の建物)。
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと(マンションなどは対象外)。
- 相続から売却までの間に、事業の用、貸付の用、居住の用に供されていないこと。
- 相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
- 売却価格が1億円以下であること。
- 売却時に以下のいずれかの状態であること。
- 家屋を取り壊して更地として売却する。
- 耐震リフォームを行った上で家屋と敷地を売却する。
この特例は、相続した実家が空き家となっており、売却を検討している方にとって有効な制度です。
詳細な要件や適用条件については、国税庁のウェブサイトをご確認ください。No.3307 相続した空き家を売ったときの特例(国税庁)
その他の節税ポイント
上記の特例以外にも、税負担を抑えるための重要なポイントがいくつかあります。
取得費が不明な場合の対処法
不動産を売却する際、譲渡所得税の計算には「取得費」が必要です。しかし、相続した不動産などで古い物件の場合、売買契約書や建築請負契約書が見つからず、取得費が不明となるケースがあります。
取得費が不明な場合、原則として売却金額の5%を「概算取得費」として計算することになります。例えば、5,000万円で売却した場合、取得費は250万円とみなされます。
実際の取得費が売却金額の5%よりもはるかに高かった場合、譲渡所得が過大に計算され、結果として本来よりも多額の税金を支払うことになってしまいます。
したがって、取得費が不明な場合でも、諦めずに以下の方法で資料を探す努力をしましょう。
- 法務局での登記簿謄本の取得:過去の所有者の履歴や抵当権設定時の情報から、間接的に取得時期や金額を推測できる場合があります。
- 金融機関の履歴照会:住宅ローンを組んでいた場合、当時の借入記録が残っている可能性があります。
- 親族への聞き取り:古い写真や日記、手紙などからヒントが見つかることもあります。
- 当時の税務申告書:贈与や相続で取得した場合、その際の申告書に取得価額が記載されていることがあります。
もしこれらの努力で取得費を証明できる資料が見つかれば、概算取得費ではなく実額で計算できるため、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
共有名義不動産の売却と税金
夫婦や兄弟姉妹などで共有名義になっている不動産を売却する場合、税金の計算は持分に応じて行われます。
- 譲渡所得の計算:各共有者が、自身の持分に応じた収入金額、取得費、譲渡費用を計算し、それぞれの譲渡所得を算出します。
- 特例の適用:例えば、夫婦で共有しているマイホームを売却し、夫婦それぞれが居住用財産の要件を満たしていれば、それぞれが3,000万円の特別控除を受けることができ、合計で最大6,000万円の控除が可能となります。
- 確定申告:各共有者がそれぞれ確定申告を行う必要があります。
共有名義の不動産売却は、単独名義の場合よりも複雑になることがあるため、事前に税理士などの専門家に相談し、適切な手続きと節税策を確認することが重要です。
不動産売却後の確定申告と納税の流れ
不動産を売却して利益が出た場合、または税金の特例を適用して税金をゼロにする場合でも、原則として確定申告が必要となります。
確定申告は、売却した年の翌年の2月16日から3月15日までの間に行う手続きであり、税金を正しく計算し、納税するために非常に重要なプロセスです。
確定申告を怠ると、税金がゼロになるはずの特例も適用できなくなり、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。
確定申告には、不動産売買契約書の写しや登記事項証明書など、多くの書類が必要です。これらの書類は、売却した不動産の種類や適用する特例によって異なります。
不動産売却後の手続きをスムーズに進めるためには、事前に必要な書類や流れを把握しておくことが大切です。確定申告や納税についてさらに詳しい情報が必要な方は、下記の記事もぜひご覧ください。
不動産売却の税金シミュレーション
ここでは、多くの方が疑問に感じるであろうケースを想定したシミュレーションと、売却時に注意すべきポイント、そして専門家への相談タイミングについて解説します。
居住用不動産を売却した場合の税金シミュレーション
ご自身が住んでいたマイホームを売却する場合、特定の要件を満たせば「3,000万円特別控除」や「軽減税率の特例」といった優遇措置が適用され、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。ここでは、それらの特例を適用した場合の税額をシミュレーションしてみましょう。
ケース1:3,000万円特別控除のみ適用(所有期間10年以下)
売却価格:5,000万円
取得費:2,000万円
譲渡費用:100万円
所有期間:8年(長期譲渡所得に該当)
譲渡所得の計算:
収入金額 5,000万円 – (取得費 2,000万円 + 譲渡費用 100万円) = 2,900万円
3,000万円特別控除適用後の譲渡所得:
2,900万円 – 3,000万円 = 0円(譲渡所得がマイナスになるため課税対象なし)
このケースでは、3,000万円特別控除の適用により、譲渡所得が0円となり、税金は発生しません。
ケース2:3,000万円特別控除と軽減税率の特例を併用(所有期間10年超)
売却価格:8,000万円
取得費:3,000万円
譲渡費用:200万円
所有期間:15年
譲渡所得の計算:
収入金額 8,000万円 – (取得費 3,000万円 + 譲渡費用 200万円) = 4,800万円
3,000万円特別控除適用後の譲渡所得:
4,800万円 – 3,000万円 = 1,800万円
この1,800万円に対して、所有期間が10年超のため、軽減税率の特例が適用されます。
| 譲渡所得 | 所得税率 | 住民税率 | 復興特別所得税率 | 合計税率 | 税額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,800万円 | 10% | 4% | 所得税の2.1% | 14.21% | 2,557,800円 |
このケースでは、譲渡所得税は2,557,800円となります。
これらの特例の詳細な適用要件については、国税庁のウェブサイトをご確認ください。 国税庁
相続した不動産を売却した場合の税金シミュレーション
相続によって取得した不動産を売却する場合も、税金が発生する可能性があります。特に、被相続人が住んでいた空き家を売却する際には、「相続した空き家を売却した場合の3,000万円特別控除」が適用できる場合があります。
ケース1:相続空き家特例を適用しない場合
売却価格:4,000万円
取得費:1,000万円(被相続人から引き継いだ取得費)
譲渡費用:100万円
所有期間:12年(被相続人の所有期間を含む)
譲渡所得の計算:
収入金額 4,000万円 – (取得費 1,000万円 + 譲渡費用 100万円) = 2,900万円
所有期間が5年超のため、長期譲渡所得の税率が適用されます。
| 譲渡所得 | 所得税率 | 住民税率 | 復興特別所得税率 | 合計税率 | 税額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,900万円 | 15% | 5% | 所得税の2.1% | 20.315% | 5,891,350円 |
このケースでは、譲渡所得税は5,891,350円となります。
ケース2:相続空き家特例を適用した場合
上記ケース1と同じ条件で、相続空き家特例(3,000万円特別控除)の適用要件を満たした場合。
譲渡所得の計算:
収入金額 4,000万円 – (取得費 1,000万円 + 譲渡費用 100万円) = 2,900万円
3,000万円特別控除適用後の譲渡所得:
2,900万円 – 3,000万円 = 0円(譲渡所得がマイナスになるため課税対象なし)
このケースでは、相続空き家特例の適用により、譲渡所得が0円となり、税金は発生しません。 相続した不動産の売却における税金は、取得費の計算が特に重要になります。被相続人が不動産を取得した際の資料がない場合でも、取得費を計算する方法がありますので、必ず確認しましょう。
相続した空き家の特例についても、国税庁のウェブサイトで詳細を確認できます。 国税庁
税務署や専門家への相談のタイミング
不動産売却における税金は複雑で、専門知識なしに正確な判断を下すことは難しいです。適切なタイミングで専門家に相談することで、節税の機会を逃さず、申告漏れや誤りを防ぐことができます。
- 売却を検討し始めた段階:
不動産の売却を考え始めたら、まずは概算の税額を把握することが大切です。
とくに住んでいた家を売る場合、売却時期や他の不動産の売却状況によって利用できる特例が変わるため、早めに税理士に相談することが重要です。 - 売却契約締結前:
売却契約を締結する前に、最終的な税金の見込み額を確定させ、売却益に対する納税資金の準備計画を立てることが重要です。
- 確定申告準備期間:
不動産売却の翌年の確定申告期間(原則として2月16日~3月15日)に、必要書類を揃えて申告を行います。
税理士に依頼することで、複雑な計算や書類作成を代行してもらえるため安心です。税務署の相談窓口も利用できますが、複雑なケースでは税理士への依頼がより確実です。
主な相談先とその役割:
| 相談先 | 主な役割・相談内容 |
|---|---|
| 税務署 | 一般的な税法の解釈、確定申告書の書き方指導、納税に関する相談。個別の節税対策や複雑なケースの相談には限界がある場合があります。 |
| 税理士 | 個別の状況に応じた税額計算、節税対策の提案、特例適用の可否判断、確定申告書の作成・提出代行。最も専門的かつ具体的なアドバイスが期待できます。 |
| 不動産会社 | 不動産の売買に関する市場動向、売却価格の査定、契約手続き、買主探し。税金に関する一般的な情報提供は可能ですが、個別の税務相談はできません。 |
特に、相続した不動産の売却や、複数の不動産を売却する場合、譲渡損失が発生した場合などは、専門的な知識が不可欠です。信頼できる税理士を見つけて相談することをお勧めします。
まとめ
不動産売却に伴う税金の計算は複雑ですが、節税に関する特例にも複数あり、知らないと損をするケースも多いため、正しい知識を持つことが非常に重要です。
不明な点があれば税理士などの専門家へ相談し、売却後の確定申告も忘れずに行い、後悔のない不動産売却を実現しましょう。
不動産売却だけでなく、相続手続き・書類作成もお任せください
ハウスプロデュースでは中古物件・空き家の買取を積極的に行っております。家屋に傷みがあったり残置物があったりなど、物件に多少難があっても現状のまま買い取ることが可能です。
処分にお困りの中古物件・空き家がございましたら、当社までぜひ一度お問い合わせください。
当社にご相談いただければ、当社提携の士業の専門家(税理士・司法書士・行政書士)のご案内も可能です。
相続登記がまだの方や、税金の計算が不安な方、何を準備すればいいかわからないという方も、しっかりサポートいたします。