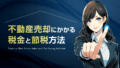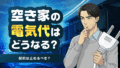実家の相続はいつ発生するかわからないものです。何から手をつければ良いか分からず不安に感じている方もいることと思います。
実家の相続で後悔しないために大切なのは、ご自身の状況に合わせて活用か売却かを早期に判断し、空き家のまま放置しないことです。
本記事では、相続手続きの具体的な流れ、実家を「所有」する場合の活用法から「処分」する場合の選択肢、税金の特例まで網羅的に解説します。
実家を相続したらまずは「所有する」か「処分する」か考えよう
実家を相したとき、最初に決めなければならないのが、その家を「所有し続ける」のか、それとも「処分(売却など)する」のかという大きな方向性です。
思い出の詰まった実家を手放すことに寂しさを感じる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、感情的な側面だけでなく、今後の維持管理にかかる費用やご自身のライフプランといった現実的な側面も踏まえて、冷静に判断することが重要です。
まずは、それぞれの選択肢のメリット・デメリットを把握し、ご自身の状況に合った方法を見極めましょう。
| 選択肢 | 主なメリット | 主なデメリット |
|---|---|---|
| 所有する |
|
|
| 処分する |
|
|
所有する場合の活用方法
実家を所有し続けると決めた場合、その活用方法は主に以下の3つが考えられます。
それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に最も適した方法を選びましょう。
自分で住む、または親族が住む
最もシンプルな活用方法が、ご自身やご家族が移り住むことです。
特に、現在の住まいが賃貸であったり、より広い家を求めていたりする場合には有力な選択肢となります。
ただし、通勤・通学の利便性や、将来的なライフスタイルの変化にも対応できるか、慎重に検討する必要があります。
また、建物が老朽化している場合は、快適に住むためにリフォーム費用がかかる可能性も考慮しておきましょう。
賃貸に出して家賃収入を得る
ご自身が住む予定がない場合は、賃貸物件として貸し出し、家賃収入を得る方法があります。 安定した収入源となり得ますが、空室リスクや入居者トラブル、建物の修繕費といった賃貸経営に伴うリスクも存在します。 また、貸し出す前には、水回りなどの最低限のリフォームが必要になるケースが一般的です。 賃貸経営の経験がない場合は、管理会社に委託することも検討しましょう。
空き家のまま適切に管理する
すぐに活用方法が決まらない場合でも、空き家のまま放置することは絶対に避けるべきです。
管理が行き届かない空き家は、急速に劣化が進むだけでなく、景観の悪化や不法侵入、放火などのリスクを高めます。
さらに、倒壊などの危険性が高い「特定空き家」や、放置すれば特定空き家になるおそれのある「管理不全空家」に指定されると、固定資産税の軽減措置が適用されなくなり、税額が最大で6倍になる可能性があります。
活用予定がなくても、定期的な換気や清掃、庭の手入れなど、適切な管理を続ける義務があります。
(参照元:空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化。トラブルになる前に対応を!|政府広報オンライン)
処分する場合の選択肢
実家を処分すると決めた場合、その方法は売却だけではありません。状況によっては他の選択肢が適していることもあります。
古家付き土地として売却する
建物を解体せずに、そのままの状態で土地と建物をセットで売却する方法です。
解体費用がかからないというメリットがありますが、買い手側がリフォームや解体を前提に購入を検討するため、売却価格が相場より低くなる傾向があります。
建物の老朽化が著しい場合は、買い手が見つかりにくい可能性もあります。
更地にして売却する
建物を解体し、土地だけの状態(更地)にして売却する方法です。
買い手は自由に建物を建てられるため、土地のエリアによっては買い手が見つかりやすく、高く売れる可能性があります。
一方で、数百万円単位の解体費用がかかる点がデメリットです。
また、更地は家が建っている土地より固定資産税が高くなるため、売却までに時間がかかると税負担が増加する点にも注意が必要です。
相続土地国庫帰属制度を利用する
売却や活用が難しい土地の管理に困っている場合に検討できるのが「相続土地国庫帰属制度」です。 これは、相続した不要な土地の所有権を、一定の要件を満たすことで国に引き取ってもらえる制度です。 ただし、建物がある土地や、管理・処分に過大な費用や労力がかかる土地は対象外となるなど、承認のハードルは決して低くありません。 また、土地の種別や面積に応じて算出される10年分の管理費相当額(原則20万円から)を負担金として納付する必要があります。
(参照元:相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」|政府広報オンライン)
実家を相続する際の流れ
相続手続きには期限が設けられているものも多く、全体の流れを把握して計画的に進めることが重要になります。
ここでは、相続が発生してから手続きが完了するまでの一般的な流れを5つのステップに分けて詳しく解説します。
1. 遺言書の有無の確認
相続手続きを開始するにあたり、まず最初に行うべきことは、被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺しているかどうかの確認です。遺言書がある場合、原則としてその内容に従って遺産分割が行われるため、その後の手続きに大きく影響します。
遺言書には主に以下の種類があります。
- 公正証書遺言:公証役場で作成される遺言書です。原本が公証役場に保管されているため、偽造や紛失のリスクが低く、家庭裁判所での検認も不要です。まずは最寄りの公証役場に問い合わせてみましょう。
- 自筆証書遺言:被相続人自身が手書きで作成した遺言書です。自宅の仏壇や書斎、金融機関の貸金庫などで保管されているケースが多く見られます。法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用している可能性もあるため、法務局への照会も行いましょう。自宅などで自筆証書遺言書を発見した場合、封がされているものは勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で相続人の立ち会いのもと開封する「検認」という手続きが必要になります。
遺言書の有無によって遺産の分割方法が大きく変わるため、心当たりのある場所を丁寧に探すことが肝心です。
2. 相続人・相続財産の洗い出し
遺言書の確認と並行して、誰が相続人になるのか(相続人調査)と、どのような財産が遺されているのか(相続財産調査)を確定させる必要があります。
この2つの調査は、後の遺産分割協議や相続税申告の基礎となる非常に重要なステップです。
相続人調査
法的に相続権を持つ「法定相続人」を確定させるための調査です。
被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む)を取得し、親子関係や婚姻関係をすべて確認します。
これにより、現在の家族構成からは分からない相続人(前妻の子など)が判明することもあります。
相続財産調査
被相続人が所有していた財産をすべてリストアップします。実家のような不動産だけでなく、預貯金、株式などの有価証券、自動車、生命保険金なども対象となります。同時に、借金やローン、未払いの税金といったマイナスの財産も相続の対象となるため、注意深く調査する必要があります。調査結果は「財産目録」として一覧にまとめておくと、後の遺産分割協議で役立ちます。
実家(土地・建物)の価値については、固定資産税の納税通知書に記載されている「固定資産税評価額」がひとつの目安になります。
3. 財産状況によっては相続放棄・限定承認を検討
相続財産調査の結果、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産の方が多い「債務超過」の状態であることが判明する場合があります。
その場合、すべての財産を引き継がない「相続放棄」や、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」という手続きを選択することができます。
これらの手続きは、相続の開始があったことを”知った時”から3ヶ月以内に、被相続人が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
もし3ヶ月を過ぎてしまうと、原則として単純承認(すべての財産を無条件に引き継ぐこと)したとみなされ、被相続人の借金もすべて背負うことになるため、財産調査は迅速に行わなければなりません。
| 種類 | 内容 | 主なケース | 期限 |
|---|---|---|---|
| 単純承認 | プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ | プラスの財産が明らかに多い場合 | 特になし(ただし、3ヶ月以内に他の手続きをしないと単純承認とみなされる) |
| 相続放棄 | プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない | マイナスの財産が明らかに多い場合 | 相続開始を知った時から3ヶ月以内 |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ | 財産状況が不明確で、債務超過の可能性がある場合 |
4. 遺産分割
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で「誰が」「どの財産を」「どれくらいの割合で」相続するのかを話し合います。 これを「遺産分割協議」と呼びます。
遺言書がある場合はその内容が優先されますが、相続人全員が合意すれば、遺言書とは異なる内容で分割することも可能です。
遺産分割協議がまとまったら、その内容を証明するために「遺産分割協議書」を作成します。
この書類には、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。
遺産分割協議書は、後の不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きなどで必要となる重要な書類です。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
5. 相続登記・相続税申告
遺産分割協議が完了したら、最後に行うのが名義変更と税金の申告です。
相続登記(不動産の名義変更)
相続した実家(土地・建物)の所有権移転登記(相続登記)は、これまで任意とされていましたが、法改正により2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続により不動産を取得したことを“知った日”から3年以内に申請する必要があります。
正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。必ず期限内に手続きを完了させましょう。
相続税申告
相続した財産の総額が、基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。
相続税の申告と納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内と定められています。
申告先は、被相続人が最後に住んでいた住所を管轄する税務署です。
相続税の負担を軽減する制度もありますが、適用には申告が必須となるため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
実家の相続で気を付けるべきこと
実家は、預貯金などの金融資産とは異なり、物理的な管理が必要で、相続人の想い入れも深いことから、相続において特有の注意点が存在します。
感情的な対立や思わぬ費用の発生を避けるためにも、事前に注意すべきポイントをしっかりと把握しておくことが重要です。
実家以外に相続財産がない場合の分割の仕方
相続財産が実家のみ、あるいは財産の価値のほとんどを実家が占める場合、分割が難しくトラブルに発展しやすい傾向があります。 不動産は預貯金のように簡単に分割できないため、相続人間で公平感を保つのが難しいからです。 このような場合の分割方法として、主に以下の4つの方法が考えられます。
- 現物分割
特定の相続人が実家を相続する方法です。例えば長男が実家を相続するなど、誰か一人が単独で所有することになります。 - 代償分割
特定の相続人が実家を相続する代わりに、他の相続人に対して法定相続分に見合う現金(代償金)を支払う方法です。実家を取得する相続人に十分な自己資金がある場合に有効な手段です。 - 換価分割
実家を売却して現金化し、その売却代金を相続人同士で分け合う方法です。公平に分割できるため、誰も実家に住む予定がない場合に適しています。 - 共有分割
複数の相続人が共有名義で実家を相続する方法です。一見公平に見えますが、後述する様々なリスクがあるため、慎重な判断が求められます。
どの方法を選択するかは、相続人全員の意向やライフプラン、実家の状況などを総合的に考慮して決める必要があります。それぞれのメリット・デメリットをまとめた以下の表も参考に、相続人全員で十分に話し合いましょう。
| 分割方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 現物分割 | ・実家を残すことができる ・手続きが比較的シンプル |
・相続人の間で不公平感が出やすい ・他の相続人の同意が必要 |
| 代償分割 | ・実家を残しつつ、他の相続人との公平を保てる | ・実家を相続する人に多額の自己資金が必要 ・不動産の評価額で揉める可能性がある |
| 換価分割 | ・相続分を現金で受け取れるため公平 ・後のトラブルが少ない |
・思い出のある実家がなくなる ・売却に手間や時間がかかる |
| 共有分割 | ・一旦、公平に分割した形にできる | ・売却やリフォームに共有者全員の同意が必要になる ・相続が繰り返されると権利関係が複雑化する |
亡くなった人の配偶者が実家を相続する場合は「配偶者居住権」
2020年4月1日に施行された民法改正により、「配偶者居住権」という新しい権利が創設されました。
この制度は、亡くなった方の配偶者が、住み慣れた家に生涯、または一定期間、無料で住み続けられるようにするものです。
遺産が自宅不動産とわずかな預貯金しかないケースで、配偶者が自宅を相続すると、他の相続人(例えば子など)に渡すための現金が不足することを防ぐ目的があります。
配偶者居住権は、建物の価値を「居住権」と「所有権」に分けて考えることで、配偶者は低い評価額の「居住権」を相続し、残りの預貯金などをより多く相続できるようになります。

遺産分割協議での合意や遺言による指定などが必要なほか、制約もあるから、制度の利用は専門家への相談をお勧めするで。
解体・リフォームの判断は慎重に
相続した実家が古い場合、すぐに解体して更地にしたり、リフォームしたりすることを考えがちですが、その判断は慎重に行うべきです。
とくに安易な解体は思わぬ不利益を招く可能性があります。
最大の注意点は、建物を解体すると土地にかかる固定資産税の優遇措置(住宅用地の特例)が適用されなくなることです。
これにより、土地の固定資産税が最大で6倍になる可能性があります。
そのため、解体後の土地の活用方法(売却、駐車場経営など)が具体的に決まってから解体工事に着手するのが賢明です。
リフォームに関しても、かかった費用以上に売却価格が上がるとは限らないため、費用対効果を十分に検討することが重要です。
いずれの場合も、複数の不動産会社やリフォーム会社に相談し、専門的な視点からアドバイスを受けることをおすすめします。
使う予定が無いなら早めに売却すべき
相続した実家に誰も住む予定がなく、賃貸などの活用計画もない場合は、できるだけ早く売却することを強くおすすめします。
空き家のまま所有し続けることには、多くのリスクとコストが伴うからです。
空き家は所有しているだけで維持管理費用がかかり続けます。
また、使っていない家は劣化が早く、資産価値が下落していきます。
さらに、管理が行き届かない空き家は倒壊の危険や景観の悪化などを招き、自治体から「特定空家等」に指定される可能性があります。
早期に売却することで、これらの維持管理コストやリスクから解放されるだけでなく、相続財産を現金化できるため、相続人間での分割も容易になります。
共有名義のリスクを把握しておく
遺産分割協議の結果、相続トラブルを避けるために実家を兄弟姉妹などの共有名義にすることがあります。
しかし、共有名義は将来的なトラブルの火種となる可能性が高いため、原則として避けるべき選択肢です。
共有名義の最大のリスクは、不動産の管理・処分に関する意思決定の難しさです。
例えば、実家を売却したり、大規模なリフォームを行ったりするには、共有者全員の同意が必要です。
一人でも反対すれば、何も進められなくなります。
もう1つのリスクは、共有者の一人が亡くなると、その人の持分がさらにその相続人へと引き継がれていくことです。
これを繰り返すうちに、面識のない親戚なども含めて共有者が増えていき、権利関係が複雑化します。
そうなると、共有者全員の合意形成は事実上不可能になり、不動産は「塩漬け」状態になってしまいます。
こうした事態を避けるためにも、遺産分割の段階で代償分割や換価分割といった方法を検討し、できる限り単独名義での相続を目指すことが重要です。
実家を相続する時に知っておくべき、税金に関する制度
小規模宅地等の特例
亡くなった方が住んでいた土地を、特定の親族が相続する場合に、土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
この特例は、主に被相続人と同居していた親族や、持ち家がない親族(家なき子特例)が利用できます。
土地の評価額が大きく下がるため、相続税の負担を大幅に減らすことができます。
(参照元:相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁)
空き家の3,000万円特別控除の特例
被相続人が亡くなって空き家になった住宅を相続し、その住宅を売却した場合、譲渡所得(売却益)から最大3,000万円を控除できる制度です。
制度の適用には以下のような条件があります。
- 被相続人が亡くなる時点で一人暮らしである。
- 1981年5月31日以前に建築された建物である。
- 更地にして売却、または耐震補強をする(補強は買主が実施でもOK) など
他の条件もあるため、適用を検討する場合は税理士など専門家に相談しましょう。
(参照元:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁)
売却する場合の取得費加算の特例
相続した不動産を売却する際に、支払った相続税の一部を譲渡所得から差し引くことができる制度です。
この特例は、相続税を納付した人が、相続開始の翌日から3年10カ月以内に不動産を売却した場合に適用されます。
この制度を利用すると、売却益が少なく計算されるため、所得税や住民税を減らすことができます。
(参照元:相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁)
相続した実家は空き家のままにしない
相続した実家に住む予定がない場合でも、空き家のまま放置することには多くのリスクが伴います。
なぜ空き家のままにしてはいけないのか、その具体的な理由と、放置した場合に起こりうる事態について詳しく解説します。
空き家のまま放置する4つの大きなリスク
誰も住んでいない家は、換気不足や清掃が頻繁にできないため、予想外に早く傷んでいきます。
長期間空き家にすることで、主に4つの大きなリスクが発生します。
1. 金銭的負担が増え続ける
空き家であっても、所有している限り様々な費用が発生し続けます。主な費用は以下の通りです。
- 税金:毎年、固定資産税と都市計画税(市街化区域内の場合)が課税されます。
- 維持管理費:庭の植木の手入れや除草、小規模な修繕など、建物の状態を維持するための費用がかかります。専門業者に管理を委託する場合はその費用も必要です。
- インフラの基本料金:水道や電気を解約してしまうと、建物の管理に支障を与える可能性があるため、基本料金を支払い続けるケースも少なくありません。
- 保険料:火災や自然災害に備えるため、火災保険への加入は必須です。空き家専用の保険は、通常の住宅向け保険よりも割高になる傾向があります。
2. 建物の老朽化と倒壊・損傷のリスク
人が住まない家は湿気がこもりやすく、もともと築年数が古い場合などは木材の腐食やシロアリ被害などが進行しやすくなります。
老朽化が進むと、台風や地震などの自然災害によって屋根や外壁が破損したり、最悪の場合は倒壊したりする危険性が高まります。
もし倒壊した建物が隣家や通行人に被害を与えた場合、所有者として損害賠償責任を問われることになります。
3. 周辺環境への悪影響と損害賠償責任
管理されていない空き家は、様々な問題を引き起こし、近隣トラブルの原因となります。
- 景観の悪化:雑草が生い茂り、建物が傷んでいく様子は、地域の景観を損ないます。
- 害虫・害獣の発生:ネズミやハクビシンなどの害獣が住み着いたり、ハチが巣を作ったりするリスクがあります。
- 防犯上の問題:不審者の侵入や不法投棄、放火のターゲットにされやすくなり、地域の治安を悪化させる一因となります。
これらの問題によって近隣住民に被害が及んだ場合も、所有者が責任を負うことになります。
4. 資産価値が下落する
空き家として放置する期間が長引くほど、建物の劣化は進み、資産価値は下落していきます。
いざ売却しようと思っても、買い手が見つかりにくくなったり、解体費用を差し引くとほとんど手元にお金が残らなかったりするケースも珍しくありません。
市場の状況によっては、土地の価値まで下がってしまう可能性もあります。
「特定空家等」に指定されるとどうなるのか
特に管理状態が悪い空き家は、行政から「特定空家等」に指定される可能性があり、所有者には重いペナルティが課せられます。
特定空家等とは
「特定空家等」とは、以下のいずれかの状態にあると市区町村が判断した空き家を指します。
- そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば、著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るためには、放置することが不適切である状態
これらの判断は、自治体が個別の状況に応じて行います。詳しくは国土交通省の公開情報もご参照ください。空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 – 国土交通省
指定された場合の流れとペナルティ
特定空家等に指定されると、行政は所有者に対して段階的に改善を求めてきます。最終的に命令に従わない場合は、行政代執行によって強制的に解体され、その費用が所有者に請求されることもあります。
| 段階 | 行政の措置 | 所有者への影響 |
|---|---|---|
| 助言・指導 | 空き家の状態を改善するよう、行政から助言や指導が行われます。 | この段階では直接的なペナルティはありませんが、改善が見られない場合は次の段階に進みます。 |
| 勧告 | 改善が見られない場合、文書で改善勧告が出されます。 | この勧告を受けても改善がみられなければ、固定資産税の特例が適用されなくなり、土地の固定資産税が最大で6倍になる可能性があります。 |
| 命令 | 勧告に従わない場合、期限を定めて改善命令が出されます。 | 正当な理由なく命令に違反した場合、50万円以下の過料が科されることがあります。 |
| 行政代執行 | 命令にも従わない場合、行政が所有者に代わって解体などの措置を行います。 | 解体などにかかった費用は、すべて所有者に請求されます。 |
空き家対策に活用できる制度やサービス
自分で管理することが難しい場合でも、空き家問題を解決するための様々な選択肢があります。
自治体の空き家相談窓口や補助金制度
多くの自治体では、空き家に関する専門の相談窓口を設けています。
専門家によるアドバイスを受けられたり、空き家の解体やリフォーム、耐震改修などに対する補助金・助成金制度を利用できたりする場合があります。
まずは実家のある市区町村のウェブサイトを確認するか、担当部署に問い合わせてみましょう。
空き家バンクの活用
空き家バンクとは、主に自治体が運営する、空き家を「売りたい・貸したい」所有者と、「買いたい・借りたい」希望者をマッチングさせるための情報提供システムです。
ウェブサイトに物件情報を登録することで、移住希望者など、より広い範囲で買い手や借り手を探すことができます。
民間の空き家管理サービス
遠方に住んでいるなどの理由で、自分で実家の管理ができない場合は、民間の空き家管理サービスを利用するのも一つの方法です。
月額数千円から1万円程度の料金で、定期的な巡回、室内換気、通水、郵便物の確認・転送、庭の草むしりといった基本的な管理を代行してくれます。
これにより、建物の劣化を遅らせ、近隣トラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。
まとめ
実家の相続は、まず「所有」か「処分」かという方針決定から始まります。
相続手続きには遺言書の確認から相続登記まで複雑な流れがあり、遺産分割や共有名義のリスクなど、後々のトラブルを避けるための注意点も多いです。
特に活用予定のない実家は、維持費や管理の手間、特定空き家に指定されるリスクを考慮し、早めの売却を検討することが賢明です。
不動産売却だけでなく、相続手続き・書類作成もお任せください
ハウスプロデュースでは中古物件・空き家の買取を積極的に行っております。家屋に傷みがあったり残置物があったりなど、物件に多少難があっても現状のまま買い取ることが可能です。
処分にお困りの中古物件・空き家がございましたら、当社までぜひ一度お問い合わせください。
当社にご相談いただければ、当社提携の士業の専門家(税理士・司法書士・行政書士)のご案内も可能です。
相続登記がまだの方や、税金の計算が不安な方、何を準備すればいいかわからないという方も、しっかりサポートいたします。